(注意 物語の内容に触れています)
石井隆による小説「GONINサーガ」(*1)は、同名映画の台本に大幅な加筆をほどこしたものと想像されるが、これを丹念に読み込むことで銀幕上の“不可視領域”にようやっと光が当たり、おぼろげだったものが姿を現わす。物語の軸心となる景色も陰影を転じて、意味合いがまるで違ってくる。
たとえば、映画においてフリーのルポライター富田慶一(柄本祐)の正体が、“五人組事件”の乱闘に巻き込まれて殉職した警察官の遺児だと割合と早い段階で示される。今は巡査の身となった己の職業身分をひた隠しにしたまま、同じく遺児として育った組員の子供に急接近し、彼らと共に上部暴力組織“五誠会”の金庫襲撃に加わることになるのだが、その際、抵抗した組員のひとり(飯島大介)に対して強盗団は発砲して、これを打ち倒している。
観客は飯島の大振りな動作と頓狂な台詞が、十九年前の『GONIN』(1995)で彼自身が演じてみせた男のそれを忠実に再現していることに気付く。また、旧作で連鎖殺人の口火となった同様の発砲が、竹中直人演じる気の触れたサラリーマンによる暴発であった事を思い出し、網膜の裏にこれを再生してデジャブに近い酩酊を味わう。どっと床に倒れてみせる姿に役者の妙味と演出の毒を感じ、記憶の甘美なるトレースを味わいながら笑いを押さえ切れずにいた訳である。
だが、闇金店長を亡き者にしたこの度の号砲を、一体誰が鳴らしたか、その点を吟味する時間は一切与えられない。私を含めた大概の観客は、雑居ビルの一隅での切迫したやり取りに五感を押し切られてしまい、そんな“些細な事”にこだわっておられないのだった。目を見開き、全てを見ていながらも、気に止める余裕が無い。
それがどうした、誰が撃ったところで関係なかろう、と考える人だって多いに違いないが、私には、観客の興味を引かないこの描写が、石井が意図的に照明を反らした“不可視領域”の好例と思える。そこからは、何らかの囁きが発せられていないか。大切な何かを語って来ないか。
原作小説に当たれば、この店長には“小池宗一”という名が与えられおり、前歴はどうだったかといえば、「あの雨の夜に死体置き場の検死を仕切っていた元マル暴の刑事」(151頁)とある。確かに言われてみれば、映画でも縁なし帽子を被った小池が病院前の駐車場にいて、暴力団員と遺族との切迫したやり取りを遠目に確認しながらも不自然に距離を置く姿が認められるのだった。
暴力団関係者が乱暴に押し寄せるのを「不審げな態度の警察官を制して」(110頁)入場させたり、団員のひとりの「松浦が小池に挨拶して、何やら情報交換をしている」(111頁)様子を石井は小説中のト書きで描いてもいるから、この当時から小池という男は裏社会に取り込まれていた訳である。こういう脇役の背景を映画では曖昧にぼかしており、小説(台本)の精読なくしては到達し得ない。
この襲撃場面では、ブレーキ無用と心に決めたらしい石井が説明を吹っ飛ばしている箇所がさらにあって、それはルポライター富田が周到に準備した変装用リアルマスクに関する仔細だ。現実にあるマスク製作会社のホームページには、写真一枚から作成が可能という記述があるが、富田もまた手持ちの写真を提供してマスクの造形を依頼したと想像される。小説中でマスクに触れる箇所を書き写してみる。石井は“不可視”を巧みに操ることがある旨、先に書いたけれど、以下の記述を読むことで納得してもらえるのではないか。
慶一が大きなバッグの中から、誰の写真で作ったのか、その人とそっくりそのまま、実物大の凹凸まで再現したリアルマスクを三個取り出して二人に渡した。
「ええええ?誰かに似てね?」
「勇人、お前にそっくりじゃね?」
「何処がですか?でも、よく似てるな~ジュニアに」
「俺じゃねって。マッポかな?」
子供のような笑顔で被(かぶ)りながら、笑いがこみ上げて来て、止まらない。(221頁)
ジュニアとは大越大輔(桐谷健太)のことであり、マッポは富田のことだ。変装用に警察の制服を準備して来たことに驚き、勇人(東出昌大)と大輔は富田のことを警察マニアと決め込むのだった。仕上がった映画においては上記の問答がほぼ全て割愛され、突如登場したリアルマスクを三人は頓着なく使用するに至るのだが、石井はわざわざ順を追って三人とは似ていないことを説明している。この持って回った台詞はどうだろう。
おまえじゃないかと振られた富田はこれに答えないから、不自然な空白がぽっかりと捨て置かれる。これから強盗に入る犯人が自分そっくりのマスクを作るはずもないし、実際映画でのそれもルポライターの顔とはそれほど似ていないから、話は尻切れトンボで終わっても無理が掛からぬ道理だ。実在する人間の顔と寸分違わぬリアルさでも、自分らと似ていなければ問題ないのだ。しかし、それにしても誰の顔なのか、どうして説明をしないのか。
マスクも、それから上の鑑識の身なりで佇む小池にしても、これ等はありありと銀幕上に現われているにかかわらず、さながら目に映らぬ霊魂のごとく“不可視の性格”をもって私たちの意識からそらされ、巧妙に隠匿されている。この油断ならぬ沈黙こそ、石井世界の醍醐味であり怖さと経験的に思う。ふと立ち止まって思案を始めると、これが実になかなか剣呑で奥深い。
奇妙な会話と前後の流れから私たちは、このリアルマスクの元となった写真は殉職した警官、森澤(富田)慶一の父親の顔を写したものに違いないと今になって確信する訳だ。ふん、それがどうした、と言う声がまた聞こえてきそうだ。最初は私もそうだった。それがどうした、“些細なこと”じゃないか、劇の大勢に影響はあるまい。だが、そこに至っておもむろに指し出される事実を何度か噛み締めているうちに、いつしか恐怖し、どうにも震えが止まらなくなる。
すなわち、森澤(富田)は父親と同じ服装と父親の顔で殴りこみをかける、そういう捨て身の、露悪的で極めて無謀な、片道切符の復讐劇に一歩足を踏み出しているのであり、かつての父親の同僚で裏切り者の元警官小池を、最初から殺すつもりで狙い撃ちしたという事が無言のまま提示されているのだった。劇中、森澤(富田)の射撃の腕は“熟達”レベルという説明もあるから、あの時、急所を外す事などいとも簡単だったろうにそれをしていない。前作の素人による偶発的な射出とは、外観こそ相似していながら全く異なる事態が発動している。現金強奪ではなく、意識的な人殺しが最初から劇の前半に置かれているのであって、蒼く冷たく燃えさかる復讐の炎が、森澤(富田)という男の全身の穴という穴から吹き上がって感じられる。
もしかしたら最初から殺すつもりだった男を葬っておきながら、黒々とした歓喜を噯(おくび)にも出さない森澤(富田)は、その後も能面のように表情を閉じ込めながら事件に関わる全てを焼き尽くしていくのであるが、何も森澤(富田)の胸中に限ってはいないのだ。これと似た重大な“不可視”が『GONINサーガ』の至るところに在るのであって、それを多角的に読み解き、上映中は思案が許されなかった空隙を埋める作業を行なうのは重要な事と思う。『GONINサーガ』の世界は確実に変貌する。変貌を経て、そこで『GONINサーガ』は完成する。
(*1):「GONIN サーガ」(石井隆 KADOKAWA/角川書店 2015) 文中の括弧内は引用頁を指す。
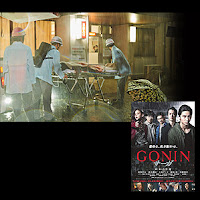

0 件のコメント:
コメントを投稿