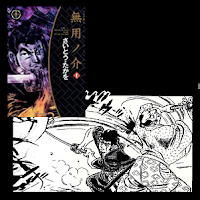2021年1月17日日曜日
“編集する者”~石井隆劇画の深間(ふかま)(10)~
2021年1月11日月曜日
“厖大な合成工程”~石井隆劇画の深間(ふかま)(9)~
2021年1月4日月曜日
“奇異なプロセス”~石井隆劇画の深間(ふかま)(8)~
漫画の描写で劇中人物の所作の極めて似るものとして、「伝統」を重んじた場面がある。「作法」にがんじがらめになる、いや、むしろ果敢に礼式に則って忘我の境地を目指そうとする、その上で先達や師との共振や邂逅を果たそうとする。つまり「道(みち)」の探求者を奇を衒(てら)わずに描くと、どうしたって所作や空気感は酷似してくる。茶道がその典型であるが、剣道や柔道といった武道においても所作はかなり制約される。神経を指先にまで配って打ち込む様子を目の当たりにして絵や写真に収めようとすれば、似通った肢体をどうしても切り取るなり描くこととなる。
【天使のはらわた】第三部(1979)、【少女名美】(1979)とは風合いに段差はあるけれど、昔から時代劇、剣豪漫画というジャンルがある。武芸に秀でた孤高の侍が全国を流浪して、行く先々で絶体絶命の場面に出くわしながらも知恵と剣術でどうにかこうにか突破していくあれだ。探していくと極めて似た構図と所作のコマに出くわす。切っ先、刃先といった殺傷能力を具えた部分を敵に向けていく物語展開上、自然と方向が生じるからだ。
実際の戦闘場面ではどうだったかは知らない。厚い甲冑を纏っての西洋での闘いにおいては斬るという行為以上に頭部を殴って脳震盪(しんとう)を起こさせることが重要視されたと聞くから、日本刀を使っての戦闘においても峰(みね)や鎬(しのぎ)と呼ばれる切れる方とは反対側の部分もがんがんと相手にぶつけ、体勢を崩した瞬間に斬りつける事もあったと思われる。実際、日本刀を手に取ってみれば、重さが手首にずんと来て、これは体感的には鬼の振り回す金棒ではないかと思う。
だか、青少年が好んで読む剣豪漫画においては、主人公は一撃必殺の達人であり、敵方の傷の痛みも我が身のそれとして感じる感受性をそなえているから、戦闘における身のこなしもあざやかであり、殴るという行為よりも切り伏せ、それも即死に至らしめる殺陣(たて)を徹底していく。剣道や居合いといった武道の作法が重んじられる流れとなるから、自ずとアクションに一定の法則が生まれる訳である。
ここで引いたのはさいとう・たかをの【無用ノ介】であるが、複数の相手が卑怯にも一斉に主人公に襲い掛かった際にさっと斬りこみ、きらめく白刃にてたちまち地に沈めてしまう場面である。左右の敵方のリアクションは異なるが、主人公の所作はほぼ同一である。これなども「所作とその捉え方、切り取り方が一致している景色」の一例である。(*1)(*2)
なにも【天使のはらわた】と【少女名美】の脱衣が「作法」に則ったやり方であるとか、一撃必殺の威力とか、男を殺すとか言いたいのではなく、漫画という媒体で考えられ得る限りの事例を並べていけばこんな物もあると言いたいのだ。そして、そのいずれとも違っている石井の特殊な技法を浮き彫りにしたいのだ。
石井作品から取り出したコマに再び注視すれば、向かって右のスカートへと伸ばされた両手首の形状、特に左手の指先の相似が目を引く。(2コマ目については後述する。)3コマ目も同様、ストッキングを足首から抜こうとしてやや力の入った右手指が表情豊かに描かれており瞳を射抜く。ここまで所作を同じくした場合、両者を「同一の存在」とコード化する読者が現われるのは避けられないし、石井もそれを承知で描いているとしか思えない。時空や境遇につき隔たりを持ちながら、【天使のはらわた】と【少女名美】のふたりのおんなは同一人物であり、決まった素振りで下穿きを脱ぎ捨てて特別な夜に臨むのである。
「土屋名美(つちやなみ)」と命名された一個のキャラクターがさまざまな物語でさまざまにおんなを演じ分けることにつき、石井の読者は百も承知であるから、今更なにを大袈裟に書き立てているのかと鼻白む人もいそうだ。確かにそうだ、どちらも土屋名美であり、どちらも似たような年齢で、同じような体型で、そっくりの服を着ていただけである。私たち石井隆の読者にとっては不思議でも何でもない。
どちらも土屋名美であるならば、服の脱ぎ方だって同じだろう。大概の場合、私たちはことさら意識せずに脱衣を繰り返しており、昨日シャワーを使った際と今日風呂を浴びた時の脱衣の様子を仮に第三者が撮影したとして、その所作に大した違いは認められないだろう。そうだなあ、上着を最初に脱ぐなあ、そしてズボンを下ろすよな、次は靴下、右が先で左が後、今のような時期にはタイツかな、そして下着のシャツ、最後にパンツだな、もう寒くていられないから、ひゃ-ひゃ-言いながら風呂に飛び込むなあ、と誰もが尋(き)かれれば自身の脱衣における手癖を直ぐに答えるだろう。土屋名美だってそうなのだ、同じ人間として服を脱ぐ順序が決まっていて、最初にスカートを下ろし、ストッキングを膝下までぐっと下げ、右足からよいしょ、と脱いでいく様子が描かれただけなんだ、そう考える読者が大勢だろう。
だが、冷静に考えてみれば、奇妙この上ない劇の展開が起きている。石井隆という創り手をいちど真剣に考えてみるに当たっては、もはや了解済みのこの「総てが名美に見える」現象について一旦そういうものと安易に納得せず、第三者目線で見直していく必要がある。
手塚治虫のスターシステム、たとえば間久部緑郎(まくべろくろう)、別名ロックのような定番キャラクターと同等の表現として土屋名美を理解して良いものだろうか。漫画の技術としてスターシステムは確立されており、次々に出現する分身を我々は苦もなく受け止め、その言動を愉しんでいく。土屋名美もそういったものだろうか。
宇宙(そら)翔る未来船のパイロットである彼と、何かの拍子に獣となってしまう特異体質者を手練手管で操って犯罪行為に突き進む1960年代の悪党である彼を、私たちはロックAとロックBと切り分けて考える。ロックAとロックBは同じ容姿ながらも別人と思う。土屋名美を私たちは互いの頭のなかでそのように明瞭に区別し得ているだろうか。どうもそうではないように思う。考えれば考えるほど特異な立ち位置にいるのが石井隆のヒロインだ。
再び【天使のはらわた】と【少女名美】の3コマに視線を戻せば、ここに描かれているのは土屋名美A、土屋名美Bではなく、もっと強力な連結が見られる。撮影する第三者の立ち位置、床面からのレンズの高低といった諸条件をも連結された場面となっている。【天使のはらわた】と【少女名美】は同一のモデルを起用した同一の写真素材を基礎として描かれた、もしくは一方が描かれた後にトレースされたと捉えるのがここでは至極自然な読解で、これを否定する人はいないだろう。
石井劇画の成り立ちが如実に現われている訳である。つまり連続して撮られた写真が先にあり、これが二つの作品(終幕間際の一場面とはいえ)を模(かたど)っている。我々が目にすることが永久に叶わないその取材写真が、【天使のはらわた】と【少女名美】のどちらか一方の劇画作品のために取材されたとするならば、同時にその事は、どちらかの作品とは当初無縁だったとも言える。先行する作品が描き込まれた後に他方でも流用されたと考えた場合、私たちはここで作品誕生のとても奇異なプロセスを間近に見ることになる。
素材写真が作品の萌芽をうながしていくことは絵画制作においては日常的であるが、それが人物を写し取った過去の写真であり、その姿態が物語の展開と作品全般の明暗を紐帯(ちゅうたい)する登場人物の真情までも雄弁に語ることは特異である。また、「連続写真」が「連続したコマ」として再生されていくことが頻繁に起こり、さらに、一組の連続写真が複数の劇画作品へと転換している点は興味深い。
漫画家は読者の視線を絶えず気にして、同じ構図、同じ姿態の描写を避ける。「手抜き」とか「安易な流用」といった負の流言を嫌って、基本は安易な反復を避けようと努めるように思われる。ここまでそっくりのコマ展開をして、揶揄されるのではなく、熱狂を産み出していった往事の石井劇画とこれを送り出した石井隆という創造者は、今更ながら稀有でとんでもない存在だったとしみじみ思う。
(*1): 「無用ノ介」① さいとう・たかを SPコミックス ワイド版 リイド社 1999 其の弐「闇の中の無用ノ介」 189頁
(*2): 同 其の参「夕日と弓と無用ノ介」320頁 「無用ノ介」の発表期間は1967年 - 1970年
2021年1月2日土曜日
“似て非なる表現”~石井隆劇画の深間(ふかま)(7)~
睡眠時の夢には脈絡なく昔日の風景なり忘れていた人物が立ち現われる。目覚めてからどうして出て来たものか訳が解らず、首を傾げることが多い。今朝のそれは以前世話になった人の面影であり、幾らか老けて見えるものの元気そうであった。往時には古いスポーツカーを大事に乗っていたのだけど、夢の中でもそれと似た車を軽快に走らせていた。
いや、おかしいぞ、と寝台で枕に顔を埋めながら暗算してみれば、現在生きていれば彼の実年齢はもっともっと上のはずである。既に鬼籍に入られていても全くおかしくない計算なのだった。夢のなかのような若々しい人相を保てるはずがなく、中途半端に歳月を重ねて珍妙な映像と思う。
いちいち夢に対して真剣に応じても詮無いことで、どうしてそんなつまらぬ話をここで持ち出すかといえば、いかに私たちの記憶はあやふやかを言いたい訳である。どんなに気合を入れて臨んだとしても正確無比に瞳に刻み、また、脳裏に完全再生することは出来ないのであって、「所作とその捉え方、切り取り方が完全に一致している」景色の復活というのは映画や漫画の特権だということ、その再確認のためだ。
さながら同一に見える風景が再度面前に展開することは、即興を徹底して禁じた芝居でもなければ見当たらない。フィルムを焼き増しして繋ぐか、丁寧に描き写すなり機械で複写してコマを再現しなければ為し得ないのだ。一種の奇蹟を映画や漫画が目の前に展開させている、この点を私たちは生理的に承知している。だからこそ作品中で繰り返し現象を目撃すると胸が瞬時にざわつき、過去の観賞時の記憶をまさぐって両者を強く結び付けようとする。
【天使のはらわた】第三部(1979)と【少女名美】(1979)の反復を意識して考え始めたとき、やにわに連想を誘ったのは粟津潔(あわづきよし)ではなくて、実は手塚治虫(てづかおさむ)の【火の鳥】であった。最初にこちらを例示した方が理解の助けになったかもしれない。
承知の通り手塚の【火の鳥】は人類史を縦断して描かれる壮大な長編連作であり、作者の死で残念ながら未完に終わっている。永遠の生命を持った火の鳥を軸に人間の欲望や愛憎を赤裸々に描いていくのだが、本当の主役は輪廻転生と時間軸のループしていく神々しい様子であろう。大過去の【同 黎明編(COM版)】(1967)より始め、次に【同 未来編】(1967-68)で超未来とその先に待ち構える人類創生を一気に描き、将来起こると運命付けられている事象として前作の一場面を組み入れている。ユニークで大胆な円環状の構成であった。天才は全く恐ろしい発想をするものである。フィルムの最後のコマを最初のコマに接合することで無限ループ的に映画が終わらなくなる、そんなイメージを最初から読者に植え付けた上で劇の詳細に斬り込んでいくのだった。
ここで引用したコマの展開がその【火の鳥 黎明編(COM版)】と【火の鳥 未来編】で別々に描かれた同一の場面である。有名な作品の有名な場面なので、ああこれか、と分かる人も多かろう。血を飲めばどんな重病人も快復するという言い伝えを信じた男が勇気を奮って火の鳥を狩ろうと試みるが、まったく歯が立たずに返り討ちに遭う場面が描かれている。(*1)(*2)
あえて近似したコマの形状と配列を行い、その中に置かれた狩人の所作を丁寧に描き直して、同じ時空であること、歴史の繰り返す様を読者に教えている。先述の「コード化」という単語を再度持ち出せば、ここではコマの配列と各描画の組み合わせから「時空間のコード化」とでも呼ぶべき事が手塚と読者の両方の認識に起きている。「所作とその捉え方、切り取り方が完全に一致している景色の復活」を私たちは見ている。
石井隆の【天使のはらわた】第三部(1979)と【少女名美】(1979)の各3コマはこれに準じた構成となっているのだけれど、繰り返しになるが【天使のはらわた】と【少女名美】の時空間は一致しないのである。
漫画の神様と誰からも尊称される手塚治虫が「時空間の同一化」はこうする、と模範的に示したものとは似て非なる表現を石井劇画は密かに為している。【鉄碗アトム】(1952-68)を愛読して育った石井が手塚に反旗を翻している訳では当然なくって、一般的な漫画の組み立て方とは全く異なる次元の創意工夫が石井劇画には注入されている、ということだろう。
それは一体何かを探っていくことが、結果的に石井作品の魅力をより際立たせることに繋がると考える。
(*1):「火の鳥 黎明編(COM版)」 初出「COM」1967年1月号 - 11月号 画像引用は角川文庫 2018 11頁
(*2):「火の鳥 未来編」 初出「COM」1967年12月号 - 1968年9月号 画像引用は 手塚治虫文庫全集 講談社 2011 280頁