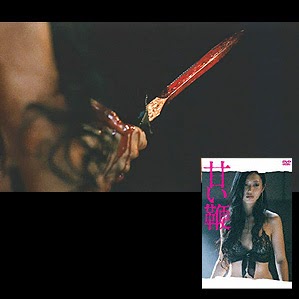凶器を握りしめたおんなが、今まさに面前の誰かを殺めんとする。刹那、別の手がにゅっと伸びて画面を横切り、刃(やいば)持つおんなの手首に躍りかかって惨劇をくい止めるのだった。『甘い鞭』(2013)の終幕にて観客の度胆を抜いた“手首掴み”の描写であったが、これに似たものを私たちは石井の過去の劇画で目撃して来た。
たとえば【天使のはらわた】(1978)において“手首掴み”は、哲郎(ここでは川島姓)と名美の関係を代弁するように象徴的に繰り返されていた。男の広い掌と指が白い手首の内側の橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっくこつ)、二本の骨を万力のごとく締め付け、挟まった神経と血管をじわり圧迫する。おんなの脳髄には電流が駆け上り、甘い官能と希望の瞬きが宿される。そんな風合いのコマが頁を覆っていた。(*1)
暴力的行為の渦中に突如割って入り、手を挿し込み、その場からおんなを離脱させようとする生一本の天性を、石井がこの哲郎という男に与えているのは明らかであって、第二部の中盤では妹の恵子に対しても同様の事を行わせている。不良グループの用心棒役となった恵子が、対立する相手に自転車のチェーンを高くふりかざし撃ち下ろそうとした瞬間、頭上から手が伸びて頭髪とチェーンをがっと摑まれるくだりがあった。
哲郎の明らかな属性として“手首掴み”のバリエーションが盛り込まれてあるのだが、捨て身で蛮行を押し止めたこの兄とその不意の出現に仰天して振り返る妹の、頁一枚をまるまる費やして描かれた両者の構図が『甘い鞭』のラストカットと重なって見えるのは、はたして偶然だろうか。石井の劇を支えるひとつの型、歌舞伎の見得と近しいものと捉えた方が良さそうだ。
【天使のはらわた】を離れて見渡せば、映画『天使のはらわた 赤い教室』(1979 監督曽根中生)の骨格となった短篇【蒼い閃光】(1976)の幕引きにも“手首掴み”が観止められる。罠に落ちてブルーフィルムに出演させられたおんなが混迷をきわめて自暴自棄に至り、手提げ鞄に隠し持っていた剃刀で自分の手首を切り裂いてしまう。その刃先は男にも向けられ、大きく傷ついた男はなんとか床を這い進んで、虫の息となって横たわるおんなの身体に必死に手を伸ばし、血を吹く手首を摑んでいくのだった。
【黒い天使】(1981)では、主人公の殺し屋魔世(まよ)を救う手のひらがあった。深夜、駐車場の前を通りかかったところ、見知らぬおんなが乱暴されかけているのを偶然目撃した魔世はこれを見過ごせずに割って入る。暴漢の逃げ去るのを確認して現場を立ち去ろうとしたところ、突然白刃がきらめいて魔世を襲うのだった。乱暴されていたおんながとち狂い、一部始終を目撃した魔世の口封じに男が置き忘れた刃物を拾ってまっしぐらに襲い掛かったのだ。刃先が魔世のみぞおちに吸い込まれる寸前、いつの間にか横に立っていた男(蘭丸)が凶刃を素手でがっと摑み、魔世の命をからくも救っている。
【蒼い閃光】のフリーライターであれ、【黒い天使】の蘭丸であれ、さらには【天使のはらわた】の川島哲郎であれ、彼らは面立ちとその人格から典型的な石井のキャラクター“村木”の系譜にあると捉えて良いだろう。これら一連のにゅっと手を出しておんなを救出する顛末は石井の活劇の王道であるのだし、このような行為の裏には常に村木的心情とでも言うべき恋慕や執心が注がれていると仮定しても一向に構うまい。
また、そのような思案の自然な枝葉として、それぞれの“手首掴み”が男女の、村木的な人格と名美的人格の再会の場に起きている点も私たちは頷きながら受け止めることが出来るだろう。当初は衝突したり眼中に置かずにいた相手が、どちらかの窮地に際してこつぜんと現れ、身とこころを救おうと懸命に手を伸ばす。無関心や誤解から散々な初対面となった二つの魂が、それゆえにどこか引き付けあって、今度こそ裏表のない真実の交信を果たそうと試みる。そういう起死回生の流れが、一連の“手首掴み”の根底に視止められる。
『甘い鞭』の終局を襲った手についての最終判断は観客のそれぞれに委ねられるし、石井も多種多様な受け止め方を喜んでいる節があるのだけれど、人によっては上に引いたような複数の残像から“村木の手”を想起することだろう。しかし、同時に私たちはそれ等の残像が付帯するものゆえに、“村木の手”の否定が厳然としてなされている点をこそ、ここではすくい取る事が可能となるのだし、むしろ求められていると感じる。
なぜあの手が男ではなく、若い無名の女優の手で演じられる必要があったのか。そうして、なぜ壇蜜がこれを振り返り、その手の持ち主が誰であるかをまったく認識出来ずに終わっているのか。
男でもなければ、再会という状況でもないのだ。ここでは“村木”の否定がくどいほど語られている。この事を読み手はよくよく咀嚼し、嚥下しなければならないだろう。『人が人を愛することのどうしようもなさ』(2007)で飛来したマネージャー(津田寛治)の魂のような湿ったものも無ければ、『ヌードの夜 愛は惜しみなく奪う』(2010)の代行屋(竹中直人)のような最期を看取ってくれる熱い腕もない。壇蜜演じる奈緒子というおんなが従来の石井の劇ではあまりない、手の届く範囲からひどく遠くに放り出されたことを示す、なんとも乾き切った終局が示されてあり、二重三重に物憂い。
幼い魂と身体を自由にせんとする犯罪行為が日々多発し、世を騒然とさせているのであるが、石井が『甘い鞭』を演出するにあたり最後の最後に“村木の不在”を深々と押印してみせたことを、善き読者を自認する者はしっかりと理解し、胸に刻んでおかなければならない。石井の犯罪にむけるまなざしや姿勢がどのようなものか、ひとりひとりが代弁する役割を担っているように私は考えている。調教、理想のおんな、馬鹿を言うな。夢を見るな、そのような暴念の果てに男の立ち位置は残されていない、村木には誰もなれない。そのような無言の叱責と共に、石井の『甘い鞭』は締めくくられている。
(*1):石井の筆づかいは腕を摑まれた名美だけでなくって、私たち読者の生理をも大きく揺さぶるものがあった。読後三十年を経ても記憶にあざやかなのは、そのリアルな肉感がわたしの奥でしっかりした切り口をつくった証だろう。石井のことを劇画家ではなく、絵描きであると感じるのはこういう時だ。