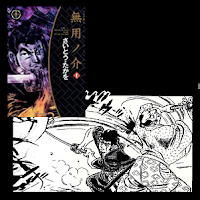【赤い眩暈】(1980)から『フィギュアなあなた』(2013)までをいわば「鳥物語」が刺し貫いている事が分かった。それとはやや足場を違えるが、最後に池田敏春(いけだとしはる)に石井が提供した映画脚本『ちぎれた愛の殺人』(1993)に触れ、この節を閉じようと思う。
『ちぎれた愛の殺人』は、石井隆と池田が公言するように、紆余曲折を経て産み落とされたいわく付きの作品である。最初に原作としてとあるミステリー小説に白羽の矢が立てられ、これに添って脚本が練られ、ロケハンとキャスティングも済み、撮入寸前に至った段階で原作者から映画化は一切ならない、自分の名前も出すなと完全拒絶されてしまった。入念なスケジュールはもう既に組まれており、いまさら俳優の日程変更など到底出来ない土壇場である。それまで部外者で居た石井は池田に頼まれ、ロケ先とキャスト等をそのまま引き継いだオリジナルストーリーを急遽組み立てるよう求められる。(*1)
普通なら匙を投げる仕事であるけれど、『天使のはらわた 赤い淫画』 (1981)、『魔性の香り』(1985)、『死霊の罠』(1988)の脚本も提供して盟友と呼べる間柄の池田であったから、石井はその危機をなんとか救おうと考えた。
本来石井隆の物語の舞台は新宿、川崎、上野、中野近辺といった都心部が主であり、実在する街並みや店舗、住居を取り込んでハイパーリアルな劇画を多作した。その手法は実際に足を運んでの思案と厖大な作画用写真の撮影が不可欠であった。それが石井劇画の凄味にもなり足枷にもなった事は否めない。上のような諸般の事情であれば、石井世界には珍しい地方都市の登場も了解出来るところだ。出雲の地名と景勝地が劇中に並び、私たちの視線は寂びれた町並を歩き、近接する断崖を目撃し、灯台を駆け上がる。
池田から最初に示されたロケ資料はいかなるものであったか分からない。石井はそれ等を睨(ね)め回しながら、決められた役者、決められた日程でどんな物語が組めるかを夢想していったのだが、それぞれのロケ地に足を運ぶことなく破綻のない話を編むことの苦労は一体どれほどだったろう。
結果はご承知の通り、異様な肉体損壊のつるべ撃ちと池田が得意とする硬質の映像美が重なる怪作となり、海外では『死霊の罠』の第三弾と位置付けられて今も時折ウェブを賑わしている。よく乗り切れたものと感心する。
喩えとして適切かどうか分からないが、この度の新型コロナウイルスの騒動に対して即座に製造配布されたm(メッセンジャー)RNAワクチンと雰囲気が似ているように思う。ドイツのビオンテック社をはじめとする研究所で開発が佳境を迎えていた正にその時期にパンデミックが起こり、直ぐに工業生産に移せたことでワクチンが行き渡ったことは僥倖であったが、同じようなことが一本の映画にも起こったのだ。
石井は既に『天使のはらわた 赤い眩暈』(1988)、『月下の蘭』(1991)を発表して監督業に手を染めており、劇画を脱して本格的に映画をやりたいという気合が漲(みなぎ)っていた。銀幕を飾るまだ見ぬ己の作品につき沸々と脳裏に浮上しては膨らみ、肺腑は極彩色の光景に染まっていた。息をすれば美しく哀しいシーンがいくらでも吐き出された。つまり、準備万端なったところに救命信号が出されたのだ。友人と思う者に対して懸命に手を差し出し、どうにか撮入の道筋を作ったものはまさしく石井の映画愛であったと感じられる。
実際、映画は石井世界に大きく舵を切った。物語は一組の夫婦、村木哲郎と名美の怨恋(うらみこい)の惨劇となって蘇生を果たしてすこぶる玄妙であり、さらに劇中の狂女の造形はヴィジュアル面で【20世紀伝説】(1995 たなか亜希夫画)と二重写しとなり、延(ひ)いては石井自身の手になる傑作『人が人を愛することのどうしようもなさ』(2007)へとやがて結実していく訳であるから、石井世界を俯瞰する上で一定の評価を得てしかるべき居住まいとなっている。
さて、そろそろ『ちぎれた愛の殺人』の「鳥」について触れよう。劇の冒頭は地方都市の海辺に遺棄された人間の胴体部分の発見で始まる。鋭利な刃物で頭部と手足を切り離された女性の遺体が消波ブロックの上に打ち上げられていて、地元の警察が来て大騒ぎになる。現場の目と鼻の先には小島が浮び、其処を無数のウミネコがうじゃうじゃと飛び交っている。
これは石井の脚本に従ったカットであるのだけど、鳥の扱いについてはやや異なっている。シナリオ誌に掲載された脚本を書き写すとこんな具合である。
2 出雲・経島(ふみしま)(早朝)
空を飛ぶウミネコ、ミャアミャアと波打ち際の岩場に
大量のウミネコが群がっていて白い肉を啄んでいる。
白い肉、女性の腐乱した胴体。(*2)
完成画面ではウミネコは作り物のおんなの胴体を警戒してさっぱり寄りつかず、残念ながら石井のたくらみ通りにはならなかった。「ウミネコがエサを漁る早朝に(撮影を)敢行。経島に群れる鳥たちに演技指導はできない」と撮影日記にあるけれど、これは思惑通りに行かなかった事を打ち明けているように思われる。(*3)
そもそも経島(ふみしま)にウミネコが大群を成して集結するのは営巣と産卵、育雛(いくすう)のためであり、これは周辺の海に餌となる魚が豊富だからだ。(*4) ウミネコは腐肉食を行なう習性はあるが、何もリスクを負ってまでしてどう見ても不自然極まりない、彼らからしたら巨大過ぎる胴体を格好の餌と捉えるはずもなく、いくらスタッフがカメラの死角に美味しそうな餌を置こうが飛んで来なかったのは道理であった。
これを書いている理由は『ちぎれた愛の殺人』の撮り損ねたところを面白おかしく論(あげつら)っている訳ではなくて、石井隆の鳥に対する生理的距離感がここで透けて見えるように思うからだ。実現ならなかった脚本のト書きを再度ゆっくりと読み直し、目を閉じてどんな絵柄が浮んで来るか想像をめぐらしてみると、極めて陰惨な風景が瞼の裏に展開される。ああ、石井隆だな、と思う。
人によっては人喰い鮫を題材にしたアメリカ映画(*5)の冒頭、砂浜に散乱するおんなの手首とその周りに群がる蟹のカットを思い出すかもしれないが、私の想像と近似するものをあえて選べば、つげ義春(よしはる)の【海辺の叙景】(1967)の中盤に描かれる海鳥のカットである。そぼふる雨の砂浜にぽつねんと佇む男の目前に、白い海鳥の群れが見える。彼らは汀(みぎわ)に出来た中洲のような狭い場所に集まり、雨の止むのを待っているだけの気配なのだが、屈託を抱えた男には自分を笑っているように見えるのか、不吉を感じるのか、その群れに傘差して近寄るとやにわに小石をつかみ投げるのだった。鳥たちは一斉に飛び立っていく。(*6)
石井が【海辺の叙景】にいくら心酔した時期を持っていたとしても、『ちぎれた愛の殺人』で当該カットを再現させようとした訳ではなく、両者は直接に結びつくものではない。「大量のウミネコが群がっている」光景とはこんな景色ではないか、という個人的な連想である。だが、石井はこの出雲の実在するウミネコの繁殖地を写真で見て、これだけ無数の鳥がいるところに細かくバラバラにした人体を放り投げれば、たちまちにして彼らは群れ寄って来るだろう、そうして鋭い嘴でつつかれてあっという間に骨になり、それも細片となって海の藻屑となって消えるに違いないと考えたのはまず間違いない。
だからこそ劇中の人物は足繁くバラバラにした死体を海辺へと持参し、崖下に投棄し続けたのである。あれは証拠隠滅の遺棄である以上にチベットの鳥葬にも似た死者に対する儀式であった。鳥をそのように使おうとした訳である。まさかウミネコたちが住むのが豊饒なる海原であり、自らの腹を充たすだけでなく、半消化のものを嘴に吐き出して雛にも与えても余りある程もイワシ、アジ、ブリが大量に回遊している場処とは思わなかったのだろう。
石井隆が鳥を見る目というのはここまで厳しく、容赦がないという点が分かるように思う。鳥と人間はかけ離れていて、感情の交流というのはなかなか行なえないのだし、両者共にその境遇なり寿命に対してなすすべもないのである。
鳥を宗教的イコンとして採用しながら、それについて懐疑的でいる。信じようとして信じ切れず、助けようとして助け切れないと思う。基本的に人間は救えないのだし、聖邪は入り乱れるのが常であるから、時には情無用に弱き者に群れなして襲いかかる。純粋な聖性などこの世にもあの世にも無いのではないか、という「見切り」が点滅する。
それは鳥に限ったことでなく、石井隆という画家が描く対象すべてに言及される距離や次元ではあるまいか。信じようとして信じ切れず、助けようとして助け切れない存在がこの世には溢れかえっている。希望と諦観、誠意と無関心、救出と不幸への後押し、両極をめまぐるしく往還するのが石井隆のまなざしであり、絵画である。その厳しさゆえに、その淋しさゆえに、石井が紡ぎ出す世界は切実で「本当の顔をしている」と思わされ、見る者の心を捕らえて離さないところがある。
(*1):「キネマ旬報 1993年7月上旬号」 「特別対談 「ちぎれた愛の殺人」で俺たちが再びコンビを組んだ理由 池田敏春 石井隆」65-69頁
「シナリオ」 1993年7月号 「腐れ縁に賭けて 石井隆」 71-72頁
(*2):「シナリオ」 1993年7月号 「シナリオ ちぎれた愛の殺人」 74頁
(*3):「キネマ旬報 1993年7月上旬号」 「撮影日記抄」 66頁
(*4):「シマネスク 島根PR情報誌」 1999年春№31 「特集 島根の野生動物」 4-5頁
(*5):『ジョーズ JAWS』(1975)監督 スティーヴン・スピルバーグ
(*6):そこに至るまでの展開で男が劇中口にする内容は、今いる海辺で昔、親子の水死体が上がったが、子供の方は無数の蛸に肉を食われて半分白骨化していたという何とも禍々しい記憶である。夏の盛りで海水浴に賑わうこの浜辺を二十年ぶりに訪れた男は、実はそんな暗い記憶に苛まれているのであってまるで元気がない。中洲に群れる白い鳥の様子は直前のその会話、蛸の巣、白骨化と共振して、読者に忌まわしき想像を促すところがある。鳥たちは茫洋として雨に耐えているだけなのか、それとも、やつらの足元に「何か」が横たわって在るのではないのか、だから群れているのではないのか。そんな不安を誘うところがある。