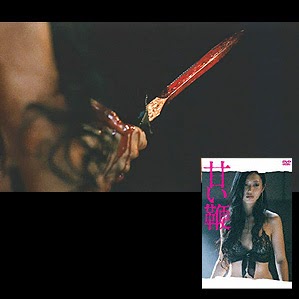石井隆の劇空間では、精神が破綻しつつあるか、それとも、激烈な戦闘に臨んで傷つき、幽明の境にたたずむ際に“全一の景観”とでも呼ぶべき境域が訪れる。それは人物の足元に滴下し、視界をみるみる覆っていくのだった。
『ヌードの夜 愛は惜しみなく奪う』(2010)のドォーモと呼ばれる巨大洞窟、『人が人を愛することのどうしようもなさ』(2007)でおんなを呑み込む記憶の混濁、『甘い鞭』(2013)の終幕に降臨する異形者のいったものが最初にあげた精神崩壊に端を発するものであり、『GONIN』(1995)の暴力団事務所の前に降りしきる幻怪なる青き雨のホリゾントなどは、その次の闘技場での景色となる。ゆらめく光と影が、私たちをひどく圧倒する。「タナトス四部作」(*1)で睡眠薬を大量に服用してみたり、水たまりに首根っこを押さえつけられ朦朧とする名美を手招きした冥府回廊も、石井隆ならではの“全一の景観”と捉えて良いだろう。こちらも網膜につよく刻まれ、生涯忘れ得ぬものになっている。
面白いことに石井の劇で“全一の景観”に取り込まれた大概の者は、衣服を剥ぎ去ることに執着する。蝉の殻(から)から抜け出る風にするすると脱衣して自身の背中を鞭打つドォーモ内での佐藤寛子や、世界はすべて我が骨と内臓とでも断ずる勢いで、電車の椅子や廃墟病院の屋上でもろ肌を晒す『人が人を─』の喜多嶋舞の姿態、放り出された雨の路上にて気がふれ、シャツや防弾着を脱ぎ捨てて裸となる『GONIN』の永島敏行という具合に列挙することはたやすい。作者の生理に基づくのか創作上の理念に因るのかは不明なれど、多発する所作として石井世界を貫いている。
彼らは衣服を剥ぎ取ることで、より一層景色に埋没なるのを念じて見える。端的にはべったりと死に撞着していて、その軌道からどうにも逃れ得ない。現実に生命を断っていく人のなかには上着のみならず肌着さえ脱ぎ捨てて素裸になり、それからおもむろに一歩踏み出す者が多くいるが、どうやら立ち位置はあれに近い。(*2)。一見エロティックに見える女優たちの脱衣も、だからデスウィッシュにまみれ、タナトスに手引きされている場合とで内実は半々だ。面差しのよく似た表土の裏には逆流する地下水系も抱えていて、思いのほか複雑な土壌となっている訳である。
読者や観客の期待に応え、ヒロインの素肌なり性愛行為を石井は多く描くのだけど、その定型にちゃんと達していながらも真逆のまなざしが注がれていることを忘れてはなるまい。(*3) その時、石井の描く人物の背景もまた妖しく変貌しており、登場人物のみならず、最終的に私たちの身体やこの想いまでも細粒化して、生と死を隔てる川向こうの闇、そして、雨へと溶け込ませんとねっとりと歩み寄って来る。石井の劇で本当にそら恐ろしいのは、肌を露わにして私たちを睨め回すおんなたちより、こっちの背景を覆うしじまではないか。
(*1):1980年に相次いで発表された小編【赤い眩暈】、【赤い暴行】、【赤い蜉蝣】、【真夜中へのドア】を指す。
(*2): 先逝く彼らの異常と言われるそれを、わたしは狂気の沙汰とは捉えない。淋しいけれども不自然ではない、という思いを抱いている。そのような切迫した局面においては、鳥が目をつつきに来るだろうか、魚や虫にじわじわ食われてしまうだろうかと憂慮するのと並行して、自身の肉体と魂が分解なり風景に溶け込んでいけるのではないかという誘惑が繰り返し人に働き、いざなっていくに違いないからだ。
石井とはまるで無関係なのだけれど、最近読んだ本も少しばかり思考に影響を及ぼしている。「被ばく列島 放射線医療と原子炉」(小出裕章、西尾正道共著 角川oneテーマ21 KADOKAWA)という薄い本で、わたしたちの肉体を一定の方向へと動かして生命を維持する分子レベルの結合に対し、このところの環境の激変がどう左右するか、憂慮する識者ふたりの意見が収まっている。広範囲におよぶ宿命的事態だから、悩んだところで身動き取れないし、こんな本を今さら手に取って悩みの種を蒔く意味はないと分かっているのだけれど、読めば読んだなりの驚きがあって止められない。
なんでも「私たちの生命を支えている分子結合」、たとえば「水素や酸素や炭素が結びついているエネルギー」というのは「エレクトロンボルトという単位で測れるほどの微小な力」であるのに対し、今回私たちの身近に風に乗って飛ばされてきた物質は低いものでも「人体の分子結合の1000倍以上のエネルギー」である「5.7キロエレクトロンボルト」とか、さらにはその百倍もの「662キロエレクトロンボルトという猛烈なエネルギー」を持っており、「そんなものが体に飛び込んでくれば、生命体を形作っている分子結合がぼろぼろにやられていくことは、分かっている」(138頁)という話だ。
読んだ瞬間にはぞっとするのみであったのだけど、しばらくしてどこか穏やかになるところも持った。私たちのこの心身は偶然にも集合したさまざまな粒子が微小な力で結束し、かろうじて構成されていて、生命活動を停止すればそれがゆるゆると崩れて細粒化し、再度世界に散っていく運命なのだと分かる。既に取り決められた定めであって、それを思うと気持ちは軽くもなるのだった。いずれ私もばらばらになり、目に見えない微細なものとなって宙を舞い、街を行き来する誰かの肩に舞い降りたり、それとも気流に乗って海を越える大冒険に出掛けるかもしれない。もしかしたらおせっかいな蝿に転生し、愛するひとの周りを飛んで危険を知らせるかもしれない。いや、既に私の手元に降りてくる雨や雪は、ひとの想いを含んだ粒子かもしれず、そうやって見渡せば世界は険しくもまた麗しいように想う。ほんの僅かではあるが、そんな空想には“救い”の味がする。
(*3):表裏(おもてうら)ある描写を常に意識して行なっている節が、石井隆という作家には至るところで視止められる。この世の事象を立場や見方を替えて凝視することを自らに課しているようで、世間でありがちな形容や理解は受容しつつも、独自の解釈で風景を組み直している。